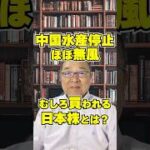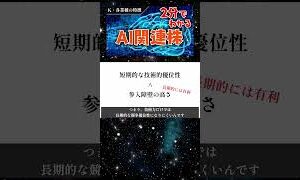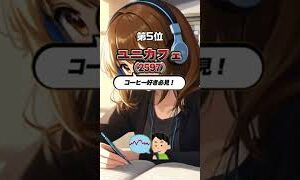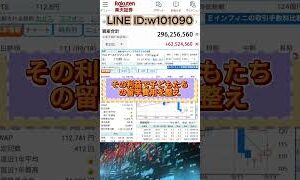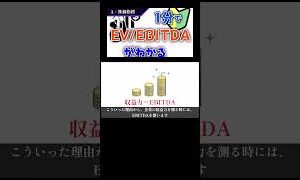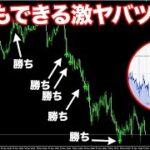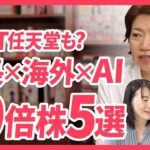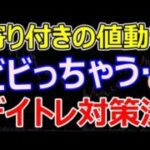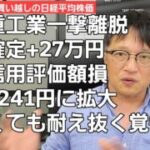🥇 格言:「節分天井、彼岸底」
📜 意味と由来
この格言は、日本の季節の変わり目の行事と株価の動向を関連付けた、
代表的な季節アノマリー(経験則)の一つです。
• 節分天井(せつぶん てんじょう):
• 時期: 2月3日頃(節分)。
• 意味: 年始から上昇してきた株価が、節分を境に天井を打ち、下落に転じやすいという経験則。
• 彼岸底(ひがん ぞこ):
• 時期: 3月の春分の日を挟んだ期間(春の彼岸)。
• 意味: 下落してきた株価が、春の彼岸頃に底を打ち、その後、新年度に向けて上昇に転じやすいという経験則。
このアノマリーが生まれた明確な由来は定かではありませんが、
新年度の始まり(4月)に向けた資金の動きや、年度末の決算を意識した機関投資家の行動が、
この時期に集中することが背景にあると考えられています。
💹 現代の投資への応用
1. 新年度(4月)に向けた資金の動き
この格言の背景にあるのは、単なる偶然ではなく、制度的な要因や税制上の要因が絡んだ資金の流れです。
• 年度末調整(節分天井の要因): 多くの企業や投資家が、3月末の決算に向けて含み益を確定したり、
税金対策のためにポジションを調整したりするため、2月頃に一旦市場の熱狂が冷め、利益確定の売りが出やすい。
• 新年度資金(彼岸底の要因): 3月の彼岸頃に株価が底を打った後、4月の新年度や新会計年度の開始に合わせて、
機関投資家や公的年金などの新しい資金が市場に流入し、株価を押し上げやすい。
2. アノマリーへの対処法
「節分天井、彼岸底」はあくまで経験則であり、必ずその通りになるわけではありません。
しかし、市場参加者の多くが意識しているため、自己実現的な形で株価に影響を与えることがあります。
• 天井付近での警戒: 2月上旬頃に株価が急騰している場合は、利益確定の売りが来る可能性を警戒し、
新規の買いを控える。
• 底付近での準備: 3月の彼岸頃に株価が下落している場合は、新年度資金の流入による反発の可能性を考慮し、
仕込みの準備をする。(ただし、あくまで企業のファンダメンタルズ分析が前提です)
3. 「もうはまだなり、まだはもうなり」との関連
この格言は、市場の転換点を見極めることの難しさ(第6回)にも繋がります。
節分の時期に誰もが「まだ上がる」と思っているときこそ天井が近く、
彼岸の時期に誰もが「まだ下がる」と思っているときこそ底が近い、という大衆心理の裏を突く教訓と言えます。
#株の格言 #株式投資 #節分天井彼岸底 #アノマリー #季節要因
#市場のジンクス #年度末 #投資のタイミング #日本株